
赤ちゃんの「首すわり」注意点を知って関われば育児はもっと楽になる!
更新日:
赤ちゃんが生まれてすぐは、毎日の生活に慣れることで精一杯だったことでしょう。しかし我が子と向き合う時間が増えたり、他の赤ちゃんと関わる機会が増えたりすると、赤ちゃんの首すわりの状態が気になることはありませんか?
首すわりは赤ちゃんの発育の過程であり、自分の目で赤ちゃんの状態を確認することは、パパママの安心につながります。
必ずしも教科書通りにいかないのが育児。ここでは、首すわりの基礎知識と首のすわりが遅い赤ちゃんの特徴、発達の確認に対する考え方をご紹介します。対処方法を知って、大らかな気持ちで赤ちゃんの成長を見守りましょう。
Table of Contents
赤ちゃんの首すわりとは

赤ちゃんの首すわりとは、赤ちゃんの首がしっかり安定することを指します。生まれてすぐは首がグラグラするため、何をするのにも気を遣いますが、首がすわると育児全般が少し楽になります。
首すわりの状態や時期、首すわりを判断する基準をみていきましょう。
首がすわるとは「自力で頭を動かせる」状態
首すわりとは、パパママが赤ちゃんの頭を支えなくても、自力で頭を動かせる状態を言います。赤ちゃんの発達の度合いを確認するうえで、パパママ同士の会話でも話題にのぼることがあるでしょう。
赤ちゃんの運動機能は、頭に近い部分から徐々に発達します。首がすわったということは、運動発達における第一歩が確認できたということ。首のすわりが安定すると、徐々に背中や腰の筋肉が発達し、寝返りやハイハイ、つかまり立ちを覚えます。
赤ちゃん自身も興味がある方向へ頭の向きを変えることができるため、これまで以上にさまざまなことに関心を示すようになります。
赤ちゃんの首すわりの時期
赤ちゃんの首すわりは個人差がありますが、目安として生後3〜4ヶ月頃です。生後2ヶ月で首すわりの兆候がある赤ちゃんもいれば、生後5ヶ月で首がすわる赤ちゃんもいます。
首すわりは以下の過程を辿ります。
| 生後2〜3ヶ月頃 | 頭を動かして、自分の意思で首を傾けようとする仕草がみられる。うつ伏せで、頭からを少し持ち上げる赤ちゃんも。 |
|---|---|
| 生後3〜4ヶ月頃 | うつ伏せで頭を45°まで上げる赤ちゃんも。赤ちゃんによっては縦抱きが可能になるが、首のすわりが不安定な場合には支えが必要。 |
| 生後4〜5ヶ月頃 | うつ伏せで頭を90°まで高く上げることが可能になる時期。首が安定し、胸と肩を挙げた姿勢をとる赤ちゃんも。 |
首すわりが確認できたら、積極的に赤ちゃんを運動に誘いましょう。発達を促すだけではなく、好奇心を刺激できますよ。
赤ちゃんの首すわりを判断する3つの基準
赤ちゃんの首すわりを判断するにあたって、医学的な基準、条件は定められていません。しかし医師は以下の動作と経験をもとに赤ちゃんの首すわりを判断します。
赤ちゃんの機嫌、体調が良いタイミングにチェックしてみましょう。
基準1:腹ばいで頭を持ち上げる
腹ばいで頭を持ち上げる動作がみられれば、首がすわったことを確認できます。支えがなくても、赤ちゃん自らの意思で動けるようになった証です。
はじめは数秒でも、次第に首回りの筋肉が発達し、長い時間頭を持ち上げることが可能になります。
頭の位置を自分の意思で動かせるようになると、徐々に頭から下の筋肉も発達してきます。しかし腹ばいを嫌がる赤ちゃんもいるため、無理強いは避けましょう。
基準2:上半身を引き起こす時に首がついてくる
赤ちゃんの上半身を引き起こす時に首がついてくる動作があれば、首がすわったと判断する基準になります。
首がすわったかどうかを判断するためのもっとも一般的な動作で、「引き起こし反応」と呼ばれています。
赤ちゃんを仰向けに寝かせ、両手を引いてゆっくり起こしましょう。首が後ろに倒れることなく、体と一緒に頭がついてくれば首が安定している証拠です。
基準3:縦抱きで頭を保持できる
縦抱きをして頭が保持できるようになれば、首がすわったと判断できます。うつ伏せを嫌がる赤ちゃんには、この縦抱きを試してみても良いでしょう。
頭が保持できれば、自分が興味のある方向へ頭を傾ける動作が出てきます。もっとも赤ちゃんに負担が少ない方法ですが、十分注意して試すようにしましょう。
首すわりは、パパママでは分かりにくいこともあります。検診時に医師の指摘で判明することもありますよ。
首すわりが遅い赤ちゃんに見られる特徴

首すわりの目安は3〜4ヶ月と言われていますが、赤ちゃんによっては遅いことがあります。
首すわりの状態によっては、疾患や障害が疑われることもありますが、ここではそれ以外の特徴と我が家の例を交えてご紹介します。
頭が大きい
頭が大きい赤ちゃんは、首のすわりが遅いことがあります。首すわりが遅いと心配になりますが、単に頭の重さを支える首の筋肉が、まだ十分に発達していないだけのこと。
成長を待てば首がすわってくるため心配はいりませんが、あまりに遅い場合には健診時に相談をしてみましょう。
我が家の子供達はこれに該当したため、首が安定するまでに5ヶ月程度かかりました。
予定日より早い出産だった
予定日より早く生まれた赤ちゃんも、首のすわりが遅いことがあります。一般的に予定日より早く生まれた赤ちゃんは、首のすわりに限らず比較的成長が穏やかです。
我が家の子供達は2ヶ月早く生まれ1ヶ月保育器で育ったため、退院してきた時は首はまだグニャグニャ。
生後3ヶ月経ってもなかなか首が安定しませんでした。親としてはヤキモキすることがありますが、ゆっくり成長する分、可愛い時期を楽しめますよ。
仰向けで良く眠る
いつも仰向けで寝ている赤ちゃんも、首のすわりが遅いことがあります。
うつ伏せ寝は乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスクがあるとの理由から、ここ最近では仰向けで寝せることがスタンダードになりました。
赤ちゃんの立場で考えれば、うつ伏せよりも仰向けの方が視界が広くなります。これを理由にうつ伏せを嫌がる赤ちゃんもいるようです。
しかしうつ伏せは、首の筋肉を強化することができます。パパママが起きている時間帯や遊びの中で、うつ伏せを促してみても良いでしょう。
首がすわる時期の赤ちゃんとの関わり方

首がすわれば育児が楽になることは確かですが、まだ不安定な時期の赤ちゃんは、目を離すと事故につながる恐れもあります。日常生活でどのように関われば育児が楽になるかを具体的にご紹介します。
縦抱きは頭と首の動きに注意して
赤ちゃんの首がすわったばかりの不安定な時期に縦抱きをする際には、頭と首の動きに注意しましょう。赤ちゃんの筋肉は、突然発達するものではありません。
前日に「首がすわった」と感じても、たまたま調子が良かっただけということも考えられます。まだ「ガクッ」とする可能性がある時期には、常に首や頭をサポートできる姿勢を保ちましょう。
抱っこ紐は月齢だけではなく、発育に沿ったものを選ぶと快適に利用できます。「縦抱き」「横抱き」「おんぶ」と3WAYタイプなら、長く使用することができるでしょう。
授乳後すぐのうつ伏せは避けて
首すわりの練習として、うつ伏せを取り入れる場合には、授乳後すぐのうつ伏せは避けましょう。うつ伏せは、お腹が圧迫されて吐き戻す可能性が高いからです。
我が家の場合、授乳後に子ども達がうつ伏せになりそうな時には、おもちゃで気を引いて時間を稼ぐという方法を取っていました。
また授乳後しばらく時間が経ってからでも、うつ伏せは「乳幼児突然死症候群」の可能性があるため、必ず大人が傍にいることを条件に取り入れましょう。
おんぶは短時間から慣らす
赤ちゃんの首がすわって、おんぶにチャレンジしたい時には、必ず短時間から慣らすようにしましょう。赤ちゃんによっては、おんぶが嫌いな子もいるからです。
またおんぶは赤ちゃんの様子が見えないため、鏡や周りの大人に確認してもらうなど、赤ちゃんのストレスにならない方法で進めることをおすすめします。おんぶされた赤ちゃんの目線で、危険なものがないかの確認も忘れずに。
縦抱きが可能になり、おんぶができるようになるとパパママの両手が使えるようになるため、外出や移動が格段に楽になります。縦抱きや前抱きができる抱っこ紐を使用して、徐々に慣らすのも良い方法です。
バスチェアの利用で一緒のお風呂が楽になる
我が家では子ども達の首すわりが安定した頃にバスチェアを採用し、お風呂が楽になりました。首が安定するまでは親子別々で入浴していましたが、バスチェアを利用することで、赤ちゃんと一緒の入浴が可能になります。
大人が身体を洗うタイミングでは、赤ちゃんをバスチェアに座らせてシャワーを当てておけば寒さで風邪をひく心配もありません。首すわりがまだ不安定な場合には、リクライニング機能が付いたバスチェアもあるため、長く使えるものをチョイスしましょう。
健全な発達を確認するためにおさえておきたいポイント

パパママ同士の会話で、「うちの子はもう首がすわった」「発達が早い」などと聞くと、「うちの子はまだだ」と弱気になることがあるでしょう。
しかし発達の速度は、競争ではありません。あくまでも健全な発育を確認するためであることを忘れないでください。
発達には個人差があって当然
首のすわりに限らず、発達には個人差があって当然です。「育児書に記載してある通りには進まない」と思っていた方が良いでしょう。育児書の目安はあくまでも平均をとったもので、前後することがよくあるからです。
我が家の例をとっても、頭が重い、早産、仰向けで寝るという特徴が重なり、首がしっかりすわるまで5ヶ月近くかかりました。
時間はかかりましたが、今は立派に駆け回っています。しかし首がすわることで、赤ちゃんの視野が飛躍的に広くなることも事実です。その後の寝返りやハイハイにもつながっていくため、その子のペースに応じた働きかけをしてあげましょう。
健診は必ず受診しよう
健全な発育を確認するために、赤ちゃんの定期健診は必ず受けましょう。3〜4ヶ月健診では医師は首のすわりをチェックします。場合によっては数週間後に再検査になることもありますが、最終的に「問題なし」となる赤ちゃんがほとんどです。
医師は首すわりの状況以外からも、赤ちゃんのさまざまな角度でチェックし、以下のような疾患や病気が隠れていないか確認します。
- 脳性麻痺
- 筋肉や骨の病気
- ホルモン異常・代謝異常
- 精神発達遅延・自閉症
首すわり以外にも、病気の可能性があれば必ず健診で指摘され、対応できる病院を紹介してくれます。ぜひ健診を受けて、赤ちゃんの健やかな成長のサポートをしてください。
首すわりのトレーニングは必要ない
赤ちゃんの首すわりが遅くても、健診で指摘を受けなければ特別なトレーニングは必要ありません。トレーニングさせようと試みても、赤ちゃんは気まぐれなのでうまくいくことの方が少ないでしょう。
普通の生活の中で、よくお世話をして可愛がってあげることが何より大切です。その流れで、マッサージや散歩、うつ伏せ遊びなど、発達に応じた適度な刺激を与えてあげましょう。
赤ちゃんは興味を持てばスイッチが入ります。パパママの関わり方次第で、普通の生活の中でもトレーニングになることがあるのです。
赤ちゃんと上手に関わって発育を見守ろう

これまでの内容をまとめると、赤ちゃんの首すわりは自力で頭を動かせる状態を言い、生後3〜4ヶ月が目安です。赤ちゃんの首すわりは、腹ばいで頭を持ち上げたり、上半身を引き起こす時に首がついてくる、縦抱きで頭を保持できるなどの確認方法があります。
頭が大きい、早産、仰向けで寝るなどの特徴があると首すわりが遅いことがあります。発達には個人差があり、健全な発育のためにも乳児健診は必ず受けましょう。
首すわりのために、特別なトレーニングは必要ありません。普段の生活の中で発達を促すことができるため、赤ちゃんの機嫌や状況をみながら、上手に関わって興味を引き出しましょう。
- 厚生労働省:乳幼児身体発育に関する調査
- 厚生労働省:「乳幼児突然死症候群(SIDS)」
- 関野小児科内科クリニック:ミニ知識No.180「首のすわり」
- 国立成育医療研究センター:乳幼児健康診査身体診察マニュアル
- 京都府:子育てQ&A「首すわりが遅い」
- 長野県:佐久保健福祉事務所「赤ちゃんのいる生活」
この記事のライター
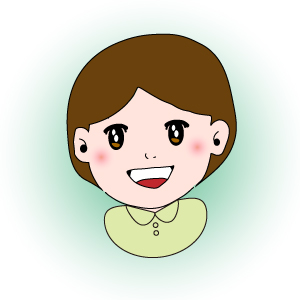
青空 太陽
【資格:病院勤務 / 診療放射線技師】
小学生の双子を育てながら、Webライターとして活動中。
双子の乳幼児期の度重なる入院・手術の経験、自身が持つ医療系国家資格を活かして、
多胎児の育児・障害児の育児についても分かりやすく発信できたらと思っています!
最近はまっていることは、調理家電をフル活用した料理とゲーム、家庭菜園。
子供達も野菜同様、まっすぐ素直に味わい深く育って欲しいと願う今日この頃です。






