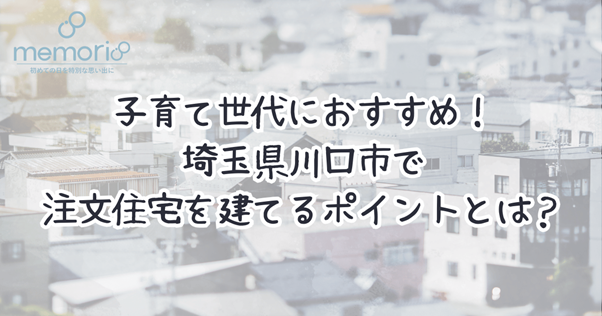里帰りしなくても大丈夫!メリットや準備、心構えをご紹介!
更新日:
妊娠が分かってから最初に考えることが、里帰りする?しない?問題です。
一般的に「出産=実家に里帰り」というパターンが多いかと思います。
しかし、様々な事情で親族に頼ることができず、里帰りしない出産を選択する人も多くいます。
筆者も子供が3人いますが、みんな里帰りせず出産。主人はとても家事育児に協力的ながら、平日は筆者の仕事が朝から夜遅くまであるためワンオペ状態。
そんな筆者の体験を振り返りつつ、「里帰りしない」出産を乗り越えた経験から、里帰りしないメリットや準備しておくべきこと、心構えなどをご紹介します。

Table of Contents
悪いことばかりではない!里帰りしないメリット
里帰りしない・できない状況の方は、様々な不安を抱えていると思います。
- 自分に育児と家事の両方が務まるのだろうか。
- 出産後すぐ動けるのだろうか。
- 陣痛や破水が起きた時一人だったらどうしようか。
このように里帰りしない出産の場合は、どうしても大変・心配な面に目が行きがちです。
しかし、里帰りしない出産にはメリットも沢山あるんです!
今回はそのメリットについてご紹介します。
通院している病院で出産できる
里帰り出産となると、妊婦健診を受ける病院と出産する病院、2つの病院に通うことになります。里帰り先が遠い場合には、実際に見ることも、受診することもなく分娩する病院を決めなくてはいけないことも。
その点、里帰りしない出産の場合は、通い慣れた病院で出産することができます。
何度も会ったことのある看護師さんや助産師さん、お医者さんがいる、気心が知れている病院で出産できることは、とても大きな安心材料になります。
環境の変化がない
里帰りをすると、どうしても里帰り先と自宅の二拠点で生活を送ることになります。
そのため、ベビーベットは自宅には用意したが里帰り先にはない、里帰り先は平屋だけど自宅には階段があるなど、ちょっとした違いがストレスになることも。
里帰りでは生活様式がガラリと変化するため、環境が変わらないことは精神的に余裕が生まれます。
パパの自覚が芽生える
妊娠している女性とは違い、男性はどうしてもパパとしての自覚が芽生えるのが遅くなりがちです。
しかし里帰りしない、パパが最初から育児に参加ことで、ママと一緒に最初から育児に奮闘し、パパとして、親としての自覚が芽生える人が多いようです。
育児にはパパの協力が不可欠です。大変な時期ですが、パパとママが協力して短い赤ちゃん期間を楽しみましょう!
自分のペースで過ごせる
実家でも、義理の両親の家だとしても、里帰りする側も迎える側も気を遣うことがあるでしょう。
ただでさえ赤ちゃんとの初めての生活で気を張っているので、少しでもストレスフリーに過ごしたいものです。
そのためサポートしてくれる人がいない、ということはとても大変ですが、誰にも邪魔されず赤ちゃんとママだけの生活リズムを作って、ゆっくり過ごすことは里帰りしないメリットと言えるでしょう。
移動する必要がない
里帰りをすると、自宅へ戻るための移動が必須です。赤ちゃんにもママにも、長時間の移動は体に負担がかかってしまいます。
また移動費はもちろん、里帰り先で使用していたさまざまなモノを運ぶ輸送費なども、かさんでしまいます。
そのため移動がないということは、赤ちゃんにも家計的にもメリットがあります。

<出産前>入院のために準備しておきたいこと
出産後の方がどうしても気になる里帰りしない出産ですが、出産前の準備もとても大事です。特に陣痛や破水が起きた時一人だった場合を想定して、様々な準備をしておかなければいけません。
そこで次は、出産前に必ずしておくべき準備を5つご紹介します。
入院準備は早めに済ませる
陣痛や破水はいつ起きるかわかりません。そのため、入院準備は必ず早め早めにしておきましょう。目安としては妊娠後期に入ったら準備を始めましょう。
また準備したものは万が一ママが自分で病院に持ってこれなかった場合を想定して、パパにも置き場所をちゃんと伝えておきましょう。
陣痛や破水が起こった場合のシミュレーションをしておく
里帰りしない場合は特に、陣痛や破水が起こった時ママが一人でいる可能性が高いです。そのため一人でも慌てずに行動できるよう、様々なシーンでのシミュレーションを想定しておきましょう。
陣痛や破水が起きたのが日中だったら?夜中だったら?買い物中だったら?自宅で一人だったら?
ママの行動パターンに当てはめて、対応方法を考えておきましょう。
陣痛タクシーの登録
陣痛タクシーというものをご存知でしょうか?
陣痛タクシーとは、事前に自宅や産院などの情報を登録しておくと、陣痛や破水が起きた時に産院まで送ってもらうことができるタクシーのことです。自家用車がある方やパパに送ってもらう予定の方も、万が一のことを考えて登録しておきましょう。
またお住まいの地域に陣痛タクシーがない場合は、タクシーの連絡先を数社分携帯に登録しておくと安心ですよ。
赤ちゃんが生まれたときの連絡先を確認
陣痛や破水が起きて病院についた時、誰も付き添いがいない可能性があります。ママが自分で連絡できればいいですが、難しい場合は病院にお願いできる場合もあります。
そのため、病院に連絡の代行を頼めるかどうかを確認し、できる場合は連絡先をまとめておきましょう。
まとめ方は、連絡相手の優先順位と、連絡が取れなかった場合の別の連絡先を書きましょう。
高額医療制度の申請
帝王切開などで高額な医療が発生した時、高度医療制度を適応できる場合があります。普通分娩予定でも、予定外の医療行為が発生する可能性は十分にあります。
そのため万が一のことを考え事前に高額医療制度の申請をしておくといいでしょう。
ママの会社の健保、もしくはパパの扶養に入っている場合はパパの会社の健保などで確認し、申請、もしくは申請方法を確認しておきましょう。
高度医療制度の申請はこちら

<出産前>産後の生活のために準備しておきたいこと
産後はバタバタ!予想以上に大変なものです。
そのため、できる限りの準備は出産前に完了しておきましょう。
続いては、出産前にしておいてよかった!と感じた5つの準備をご紹介します。
赤ちゃんグッズの整理
必要最低限の赤ちゃんグッズの購入や(ベビーベットなどがある場合は)設置は済ましておきましょう。また、購入した赤ちゃんグッズの使い方の確認もしておきましょう。
哺乳瓶の消毒や、短肌着などの下着の着方など、意外と使い方を確認しないとわからないものがあるので要注意です。
日用品・食品をストック
産後は買い出しなどに出かけなくてもある程度生活できるよう、準備しておくと後々楽になります。
筆者が買いだめしておいてよかったと特に感じたのは、お菓子です。ご飯を作る時間がないほど忙しい日々が続きますので、ちょっとした時につまめるお菓子はとても重宝しましたよ。
赤ちゃんの生活で最初はいっぱいいっぱいになってしまいがちですので、少しでもできる準備はしておきましょう。
宅配サービスの登録
産後の買い出しはとても大変です。ママが回復していない体で幼い赤ちゃんを連れ出して買い物に行くのは、できれば避けたいものです。
そのため、自宅に生活必需品を届けてくれるサービスを利用しましょう。宅配サービスの中には、1週間に1回まとめて注文するものや、注文した当日に届けてくれるものなど様々あります。
実際に使用せずとも登録しておくだけでも安心材料になりますよ。
各自治体の産後ケアの登録
地方自治体によっては、産後ケアの事業があります。内容は自治体によりますが、泊りがけで母子共に休めるものや、家事代行など様々です。
親族にサポートを頼めない場合は、このような第三者の支援を受けることを検討してみましょう。
ぜひ時間がある時に、お住まいの自治体を確認してみましょう。
上の子どものお世話方法の見直し
里帰りしない出産が第二子以降の場合、上の子どものお世話について考える必要があります。
ママが動けない間、上の子のお世話をどうするか?園や習い事に行っている場合は送り迎えを誰に頼るか?など、イレギュラーに動かなくてはいけないことが出てきます。
上の子どもの年齢により、対応は異なると思います。ぜひご家庭にあった方法を検討してみてください。

<出産後>心がけておきたいこと
出産した後はバタバタで休む暇がなく、想像以上に時間や気持ちに余裕がなくなってしまいます。そんな日々が続きどうしても気分が落ち込んでしまうことも。
しかし赤ちゃんのためにも、できるだけ笑顔で過ごしたいものです。
そこで次に、出産後に心がけておきたいことを5つご紹介します。
産前と体が違うことを理解しよう
産前と産後では、そもそもママの体は大きく変化しています。交通事故並みのダメージとホルモンバランスの崩れで、実際に感じている以上に体は悲鳴をあげています。
そのため、産前のように動けないことは当然!と考えましょう。産前と体が違うことを、ママはもちろんパパも十分理解しておきましょう。
産褥期はなるべくゆっくり過ごそう
産褥期は、里帰りせずともゆっくり休みたい時期です。とはいえ、サポートしてくれる人がいなければずっと寝ていられないのが現状です。
そのため、あらゆるサービスやモノを活用しながら1ヶ月間は休むことを第一に考えましょう。極力横になり、体が回復するように意識的に休憩してください。
手抜きを悪と思わない!
里帰りしないママの中には、ついつい頑張ってしまう方がいます。赤ちゃんのお世話は必要ですが、家事は手抜きができます。食事が出前やインスタントでも、掃除や洗濯をしなくても生きていけます。
手抜きは悪ではなく、ママの回復に必要不可欠な時間の確保です。そのため、手は抜いていいのだ、という考えにシフトしてみましょう。
使えるものは人もモノも制度もフル活用
里帰りはできなくても、ご両親や親族、パパなどに協力をお願いできるのであれば、思いっきり甘えてママはできるだけゆっくりしましょう。もしそれらが難しい場合には、お住まいの自治体の産後ケア支援を検討してみてください。
さらに食洗機やお掃除ロボットのようなハイテク家電や出前の食事などの導入も検討してみましょう。ぜひ活用できるものは全て活用して、ママの休む時間を確保しましょう。
ママが笑っていることが子どもにとっても幸せ
産後は思い通りに行かないことだらけで、気分が沈んでしまうことがあると思います。でも、子どもにとってママが笑っていることが一番です。
サポートなく退院直後から赤ちゃんを育てているだけで、とても立派なことです。ママは自分をたくさん褒めて甘やかしてあげてください。
頼れるものは頼って、完璧を求めず、少しでも休みながら笑顔で毎日を過ごすことを心がけましょう。

<体験談>里帰りしない出産で感じた大事なこと
産前の準備
産後はとても忙しくなります。産後余裕を持って過ごすためには、産前の準備が何よりも大事になってきます。
産前も体が重く大変だとは思います。それでもこの記事などを参考に、時間にも気持ちにも余裕があるうちにできることは済ましておきましょう。
感情のコントロール
産後は感情がジェットコースターのように上下します。生まれた喜びや、産後の痛みが辛く寝れない暗い気持ち、赤ちゃんの可愛さに癒されたり、できないことが多く沈んでしまう気持ちなど。
そのことを理解し、感情をコントロールできるようにしましょう。
完璧を求めない
産後は考えている以上にできないことが多いです。体が上手く動かず、気持ちに体がついていかないことも。
そのため、誰よりもママが完璧を求めず、適度に手を抜くようにしましょう。そして周囲の力を借りながら、毎日を過ごしましょう。
笑顔と赤ちゃんへの愛情
産後は精神的にも体力的にも厳しい日々が続きます。そのためどうしても、赤ちゃんを可愛いと思えなくなってしまうこともあります。
何よりも大事なのは、ママの笑顔と赤ちゃんへの愛情です。ママがやらなくてもいいことはできるだけ周囲の力を借りて、ママは笑顔で赤ちゃんに接するようにしましょう。
サポートしてくれる人サービスへの感謝の気持ち
ママが大変な時、パパやご両親、親族や自治体などのサービスにぜひ頼ってください。けれど、サポートしてくれることを当たり前と思わず、感謝の気持ちを持って力を借りましょう。
産後でバタバタしていると、自分で精一杯になって感謝の気持ちを忘れてしまいがちです。後になって反省や後悔をすることがあるので、感謝の気持ちはなるべく声に出して相手に伝えましょう。

イメージを膨らませて、動けるうちに準備を整えておきましょう!
里帰りしない出産は、間違いなく大変です。
しかし一方で、里帰りにはないメリットもたくさんあります。準備さえしっかりと整えておけば、里帰りしない出産でも大きく負担を軽減することができます。
ぜひこの記事を読んで、里帰りをしない場合のイメージを膨らませて不安を解消してくださいね。
この記事のライター

小鳥遊きさ
令和生まれの年子を育てる、主人のことが大好きなアラサー主婦です。 主人の転勤で、完全に未知なる土地で出産、育児を行なっています。 里帰りなし!親族の協力ゼロ!手伝ってくれる人は主人だけ!という環境のもと、 髪を振り乱し、白目を剥きながら、365日24時間チビ怪獣たちと格闘しています。 悩み、奮闘する1人のママとして、経験してきたことなどを発信していけたらと思います。 また趣味の料理や旅行をゆっくりできる日を夢見て、今日も主人と2人頑張ります!