
出産祝いを職場の同僚に贈る時の金額・相場と「人気のおすすめ商品10選」
更新日:
職場で出産祝いを贈る際に、もっとも悩むのは金額ではないでしょうか。しかしいくつかのポイントをおさえれば、同僚の記憶に残る出産祝いを贈ることができます。
本記事では、出産祝いの相場やマナーだけではなく、同僚のパートナーにもスポットを当てて出産祝いを解説します。参考にして、同僚に喜ばれる出産祝いを贈りましょう。
Table of Contents
同僚に贈る出産祝いの金額・相場

同僚に出産祝いを贈る場合には、以下の金額を参考にすると良いでしょう。
お返しを用意するケースが多いため、あまりに高額だと対応に困ってしまいます。立場別に具体的な金額を確認しましょう。
ケース1:同期に贈る場合
自分と同期に出産祝いを贈る場合には、気を遣わない3,000円〜5,000程度が相場とされています。
友人・知人の場合の相場は3,000円〜10,000円なのでやや少ない印象ですが、連名や部署ごとに渡すケースが含まれているためです。
金額は相手との関係性にもよりますが、周囲の同僚とも相談してあまりかけ離れない金額を贈ることをおすすめします。
高額なお祝いを贈ってしまうと、贈られた側がお返しを準備した際に、職場で渡しにくくなるためです。
ケース2:部下・後輩に贈る場合
部下や後輩に出産祝いを贈る場合には、3,000円〜10,000円が相場です。自分の方が立場が上の場合、多めに出すという考え方があるため、同期に贈るケースより高くなる傾向です。
過去に出産祝いを贈った部下・後輩がいる場合には、金額の差が出ないように配慮しましょう。お祝いとしての金額を一律にして公平性を保ちます。
親しい部下・後輩に多めに出産祝いを贈りたい場合には、現金と一緒にプレゼントを贈ることをおすすめします。
ケース3:上司・先輩に贈る場合
上司・先輩に出産祝いを贈る際には、5,000円〜10,000円を想定すると良いでしょう。日々の感謝を伝える意味で、多めに包む傾向にあります。
関わりが少ない上司・先輩の場合には、5,000円でも問題ありません。
上司・先輩という立場上、職場でこれからお世話になる場面もあるかもしれません。今後のかかわり方を考えて、迷ったら贈っておくことをおすすめします。
プラスαで感謝の気持ちを伝えたい場合には、お花やお菓子を添えると良いでしょう。
ケース4:連名で贈る場合
同僚に連名で出産祝いを贈る場合には、1人あたり1,000円〜5,000円が相場です。
合計金額が4・9のつく数字にならないよう配慮しながら、10,000円〜30,000円で出産祝いを調整しましょう。
最低でも1人あたり1,000円以上を検討して
連名で贈る際には、最低一人あたり1,000円以上を検討しましょう。あまりに少額だと、贈られた側がお返しに困るというケースがあるからです。
また一人ひとりの金額は必ず一律にするのが一般的です。金額がバラバラだと、贈られた側がお返しを選ぶ際に考えてしまいます。
有志連名で贈る際には、可能であれば割り切れる人数で贈ると、贈る側も贈られる側も負担が少なくて済みます。
連名の場合は名前の書き方に注意
連名で出産祝いを贈る場合には、名前の書き方に注意が必要です。目上の方の名前を中央に書き、役職順または年長順に右→左へと書きます。
部署として出産祝いを贈る場合には、「〇〇部 一同」。
有志連名として贈る場合には3名までなら熨斗に記載し、それ以上の場合には「代表者氏名+他〇名」とし、メンバーリストを同封するとスマートです。
同僚に出産祝いを贈るときのマナー

職場の同僚は、どちらかが転職をしない限り今後も長いお付き合いになります。
将来的により気持ちよい関係性が築けるよう、同僚に出産祝いを贈る際のマナーを確認しましょう。
御祝儀袋を準備して
出産祝いを贈る場合には、熨斗がついた御祝儀袋を準備しましょう。昔は慶事にのしアワビを贈り物として添えていたことに由来します。
のしアワビは貴重な保存食であったことから、長寿や良縁をもたらすものとして、現在の簡略化された形として残っています。
表書きには、黒の濃い毛筆を使用しましょう。上部には「御出産祝」と大きめに書き、下部には名前を少し小さめに書くとバランスよく仕上がります。
連名で男女混合のケースでは、男性の名前を先に書きましょう。
出産前には贈らない
出産祝いは、出産後に贈るのがマナーです。最近では、日本でも「ベビーシャワー」を行う習慣が増えてきたため、誤解が多く注意が必要です。
ベビーシャワーには、これから控える出産を応援する意味が込められています。
一方で出産祝いには、無事出産を終えたお祝い、赤ちゃんの健やかな成長への願いが込められています。
出産というイベントは、赤ちゃんもママも命がけのこと。よって出産祝いは、赤ちゃんとママの健康が確認されたあとに贈ることが一般的です。
避けた方がよいプレゼント
出産祝いとしてプレゼントを贈る場合、避けた方が良い品物があります。リクエストを受けた場合はこの限りではありませんが、昔から縁起が悪いとされているものに以下のようなものがあります。
- 包丁
- ハンカチ
- 緑茶
刃物は「縁を切る」とされていることから、お祝い事には避ける事が一般的です。
ハンカチは「涙を拭う」という意味があり、緑茶は弔事で用いられることが多いため避けた方が良いでしょう。
また緑茶はカフェインを含むため、授乳中は控えるママが多くいます。
会社の同僚におすすめのプレゼント

出産祝いとしてプレゼントをもらうと単純に嬉しいですが、育児中のパパママには実用性が高いものや長期にわたって使えるものが喜ばれます。
同僚への出産祝いとしてふさわしいプレゼントをご紹介します。
置き場に困らない商品券やギフト券
同僚からのプレゼントは、置き場に困らない商品券やギフト券が人気です。場所をとらずに、必要なものを必要なときに買えるため、お金と同等に喜ばれます。
「消えもの」のため、気軽に贈ることができる点がメリットです。
その一方で、金額が明確であるというデメリットも。どこでも使えるギフト券も重宝しますが、乳幼児用品を扱うチェーン店のギフト券も人気です。
迷ったときはカタログギフト
迷ったときはカタログギフトもおすすめです。カタログギフトは金額が分かりにくいうえ、必要なものを選べるというメリットがあります。
その一方で、「選ぶ手間」が面倒というデメリットも。慣れない育児に奮闘するあまりに、カタログギフトをめくる時間さえ惜しいというママもいます。
私は実際にいただきましたが、ページをめくる時間が育児の気晴らしになりました。パパママの性格や育児の様子を聞いたうえで検討することをおすすめします。
オムツやミルクなど実用的なもの
出産祝いとしてオムツやミルクなどの実用的なプレゼントも喜ばれます。消耗品や必ず使うものは、いくらあっても困りません。
しかし事前にメーカーを調べておかないと「結局使わなかった」という事態も。オムツやミルクをプレゼントとして贈る際には、必ずパパママにメーカーや素材を聞いておきましょう。
さらにオムツケーキやデコレーションなど、ラッピングにこだわると喜ばれること間違いなしです。
品物は男性目線で選ぶのもおすすめ
品物を贈る際には、男性目線で選ぶと失敗がありません。ママだけではなくパパも使いやすい色・デザインだと、積極的に育児に関わることが期待できるからです。
出産祝いとして抱っこ紐やベビーカーを贈る場合には、できるだけシンプルでシックな色合いのものを選びましょう。ブラックやカーキ、オレンジといった色なら男性でも違和感なく使えます。
サイズが大きい男性でも、取り扱いが容易なものを選ぶとなお良いでしょう。
相手別:同僚への出産祝いに人気のおすすめ商品10選
ポイントをおさえたところで、同僚への出産祝いには具体的にどのようなプレゼントが良いかを確認していきましょう。
同期に贈る場合
「おめでとう」の気持ちはもちろん、「同期ならでは」の贈り物をご紹介します。パパママのキャラクターに応じて商品を選ぶと、より喜んでもらえますよ。
赤ちゃんに優しいベビーギフトセット

出典元:楽天市場
ファンケルのベビーギフトセットは、皮膚科専門医が監修しているため、生後すぐから使用することができます。
退院して間もなくの頃は、生活に慣れるのに精いっぱい。「赤ちゃんのスキンケアにまでこだわれない」というパパママも多いはずです。
ベビー全身泡ウォッシュ・ベビーミルクのほか、オリジナルスタイを専用ギフトボックスに入れてお届けしてくれるため、「特別感」を演出できます。
赤ちゃんの身長が計測できるタオル

出典元:楽天市場
仲が良い同期の同僚におすすめしたいのが、赤ちゃんの身長が計測できるタオルです。
大漁旗をデザインしたタオルに名前が入り、新しい人生の船出を応援する気持ちを表現できます。写真映えもバッチリ。
タオルには120㎝まで計測できる目盛りが付いているため、赤ちゃんの成長が一目瞭然。毎日のお風呂上りにチェックすることができます。
部下・後輩に贈る場合
部下・後輩に出産祝いを贈る場合には、「オリジナル性」より「気の利いたもの」を選ぶこと。
直接聞ける間柄なら、事前にプレゼントの方向性をリサーチしておくと良いでしょう。
税込5,000円以下で買える食器セット

出典元:楽天市場
BABY BJORNの食器セットは、おしゃれな色合いが特徴。セットアイテムは、スタイ・プレート・カップのほかスプーン・フォークが付いています。
素材は、忙しいパパママを気遣った食洗機対応。BPA FREEで、健康への影響も配慮しています。
「自分で食べる」をサポートするため、プレートの形も特徴的。これなら小さな手でも、最後まで諦めることなく食べきることができます。
「おめでとう」が詰まったカタログギフト
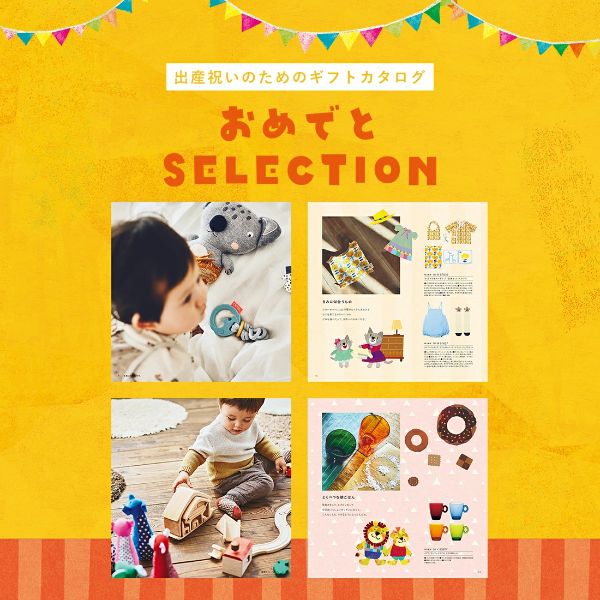
出典元:楽天市場
こちらのカタログギフトは、ギフトカタログのほかに絵本と歌動画、パズルがセットで贈れることが特徴です。もちろん、カタログの内容は赤ちゃん向けのおもちゃや役立つグッズなど充実しています。
1度で何度も楽しむことができるため、「贈って終わり」ではなく、「出産祝い」の余韻を感じてもらうことができます。
「人と違ったカタログギフトを贈りたい」という方におすすめです。
上司・先輩に贈る場合
上司・先輩に贈る場合には、ワンランク上のプレゼントを意識して。おしゃれで「見ているだけで癒される」ものをチョイスしましょう。
おしゃれなおむつボックス

出典元:楽天市場
出産祝いらしい優しい色合いのおむつボックスは、おしりふきのフタ、リボン、7種類のおむつが付いています。
おむつを使い比べる機会はなかなかないため、「どのようなおむつが合っているのか」を知ることができます。
ボックスは横幅31㎝、奥行き21㎝、高さ13㎝なので、おむつを卒業してからも収納ボックスとして使うことが可能です。
シンプルなデザインなので、おもちゃボックス以外に食料品やタオルなどの収納にも重宝します。
ポンチョと靴下のセットポンチョと靴下のセット

出典元:楽天市場
ぽんちょと靴下のセットは、秋〜冬生まれの赤ちゃんにおすすめです。筆者は子ども達の退院日が決まったときに、慌てて買いに走った記憶があります。
パパママの許可が得られるなら、「もし良かったら退院するときにでも使ってね」と事前にプレゼントするのもおすすめです。
パパママは、退院後の生活を想像するもの。「退院時」の服装までは気を配れない事があります。
ギフトに最適なおむつケーキ

出典元:楽天市場
おしゃれなタオルとソックスが付いたおむつケーキです。どちらも好みのカラーから選ぶ事ができ、靴下は女の子向けのデザインから選択もです。
タオルはオーガニックコットン100%で、贅沢なボリューム感を味わえます。タオルとソックスがベーシックなデザインなので、「大人っぽいおむつケーキを探している」人におすすめです。
連名で贈る場合
連名で同僚に出産祝いを贈る場合には、「華やかさ」を意識することがポイント。
育休中のパパママなら、プレゼントと一緒に「早く一緒に仕事をしたい」という気持ちを届けることができますよ。
あれこれ詰め込んだ出産祝いセット

出典元:楽天市場
連名で出産祝いを贈る際には、色々な意見が出ることがあるでしょう。これなら「あれもこれも詰め込んである」ため、意見を反映させることができます。
タオルやおもちゃ、おしゃぶりなどすぐに使えるグッズが5点も入っているため、見た目も華やかで、贈られた方も楽しい気持ちになるでしょう。
大きくなっても使える人形つきおむつセット

出典元:楽天市場
人形付きのおむつセットは、見た目の豪華さだけではなく、赤ちゃんに「人形」を贈る意味でもおすすめです。
大きくなってからなかなか寝付けないときに、赤ちゃんの頃から使っている人形を渡せばストンと眠りに落ちることも。
「記憶」や「におい」が影響していると思われますが、小さなときから「入眠グッズ」の意識づけができます。
セットのタオルは、今治タオルで毛足が長くふっくら。赤ちゃんの敏感な肌を優しく拭くことができます。
長く使える知育玩具のセット

出典元:楽天市場
同僚への出産祝いに、知育玩具もおすすめです。こちらのセットなら、「いかにも知育玩具」という作りではなく、人型ドミノの表情もキュート。
ドミノの1つに名入れができるため、スペシャル感を演出できます。
セットはドミノのほか、タンバリンやカスタネットなどがあり、聴覚を刺激することも可能。収納バックが付いているため、お出かけや片付けに便利です。
出産祝いはいつ贈る?

出産祝いは、生後1週間〜1ヶ月前後で贈るのがベストとされています。出産報告を受けると、すぐにでもお祝いしたい気持ちになりますが、ママと赤ちゃんの体調が整うまで待ちましょう。
出産祝いを贈る際には、適切なタイミングを選ぶのもマナーです。
訪問する場合は母子の体調を確認する
直接自宅を訪問して出産祝いを贈る場合には、必ず母子の体調を確認しましょう。出産は命がけのイベント。
ママだけではなく赤ちゃんが新生児集中治療室(NICU)や保育器に入っていることも考えられるため、訪問の時期は必ず同僚にお伺いを立てましょう。
あくまでも出産がスムーズで無事に退院して生活のリズムができるのが、生後1週間〜1ヶ月前後という時期です。我が家の場合赤ちゃんが小さく生まれたため、はじめて同僚が自宅に来たのは半年後でした。
前もって「お祝いを届けたい」と同僚に話せば、具体的な時期を提示してくれるはずです。
渡し方にこだわらず郵送でもOK
出産祝いを贈る際には郵送でもOKです。訪問が難しい、贈るタイミングが遅くなってしまうなどの場合には、郵送を利用しましょう。
また郵送を利用すると、相手側の負担を減らせるというメリットがあります。
育児に忙しい時期に、相手としてはお茶菓子を準備したり赤ちゃんのお昼寝の時間を気遣ったりするのは負担です。
どうしても直接渡したい場合には、ひとこと声をかけて産休明けや相手の都合が良いタイミングで渡しても良いでしょう。
メッセージを添えて同僚を喜ばせよう

出産祝いと一緒にメッセージを添えると、お祝いする気持ちをより明確に伝えることができます。
相手も「祝福されている」と実感するため、出産祝いをよりハッピーなイベントにすることができるでしょう。
不安が吹き飛ぶような明るい言葉を選んで
メッセージを添える際には、不安が吹き飛ぶような明るい言葉を選びましょう。命がけのイベントを終えたパパママを労う言葉がベターです。
「ご家族のますますの幸せをお祈りしています」「赤ちゃんの成長が楽しみです」同僚の忙しさを気遣ったり、自分が言われて嬉しい言葉を選ぶと良いでしょう。
とくに出産祝いを贈る時期は正しい育児ができているのか迷いが生じる時期。明るい言葉で不安を吹き飛ばしてあげましょう。
職場でのイメージを添えると嬉しくなる
メッセージには、同僚の職場でのイメージを添えると喜ばれます。「一緒に頑張りたい」「早く復帰したい」という、仕事に前向きな気持ちを持てるからです。
「いつも明るい〇〇さん。きっと赤ちゃんも明るい子に育つでしょう」「いつでも頼りになる〇〇さんの復帰を社員一同お待ちしています」
「職場の人間だからこそ知っている姿」を改めて文字にされると、照れくさいと同時に嬉しい気持ちになります。
職場でのイメージを上手にとり入れて、友人・親戚とはひと味違ったメッセージを添えましょう。
同僚とパートナーが喜ぶ出産祝いを贈ろう

出産祝いは同僚だけではなく、一緒に子育てをするパートナーのことも考えて贈ると喜ばれます。
男性に贈るなら「母子ともに健康と聞いて安心しました」、女性に贈るなら「頼りになるパパで羨ましいです」など、さりげなくパートナーを気遣う言葉を添えましょう。
もちろん出産をお祝いする気持ちとマナーも忘れずに。素敵な出産祝いをきっかけに、職場の人間関係を深めることができるかもしれませんよ。
この記事のライター
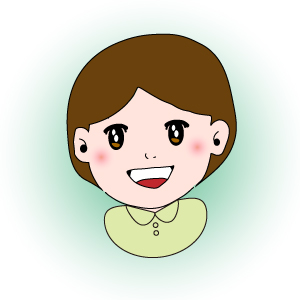
青空 太陽
【資格:病院勤務 / 診療放射線技師】
小学生の双子を育てながら、Webライターとして活動中。
双子の乳幼児期の度重なる入院・手術の経験、自身が持つ医療系国家資格を活かして、
多胎児の育児・障害児の育児についても分かりやすく発信できたらと思っています!
最近はまっていることは、調理家電をフル活用した料理とゲーム、家庭菜園。
子供達も野菜同様、まっすぐ素直に味わい深く育って欲しいと願う今日この頃です。






